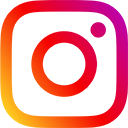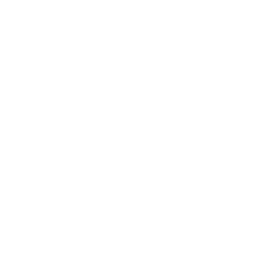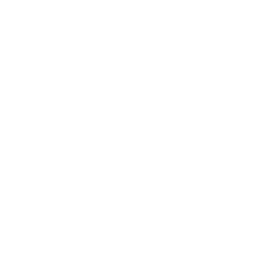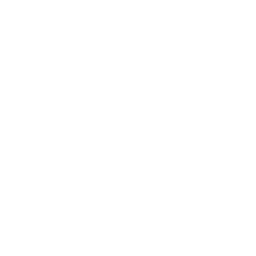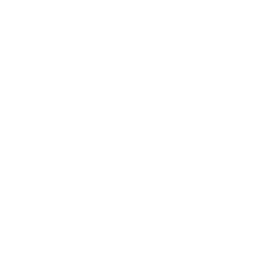学校紹介 奈良高専
今回は大和郡山市にある奈良高専について紹介していきます
高専とは
そもそもの話、「高専(こうせん)」とは…なんですが、全く知らない方からは高校?工業高校?専門学校?何が違うの?とよく聞かれます
高専を略さず言うと「高等専門学校」で「高等」と付くのがポイントでしょうか
より高度な研究ができる・就職に必要な技術を身に着けられるというのが高専です
そういう意味では工業高校や専門学校に近しいところもありますが”高度な”研究ができるというのが、高専の特徴かと思います
奈良県内で高専の話をした時によく言われるのは「頭が良い子が行くところだよね」でしょうか
個人的には確かに頭が良い子は多いけれども皆一筋縄ではいかないというか、キャラが濃い子が多い印象です
濃い…というのがそれぞれの興味の対象への熱量に比例するところでもあり、専門的な話をしだすと大抵の人が饒舌になります
そして話をする目を輝かせ嬉しそうにしているので「専門的過ぎてよくわからないけど、凄く”好き”なのはわかる」という風なオタク気質というかそういった雰囲気を漂わせています
面白いのは高専出身の人は他の高専出身の人と会った時も”高専っぽさを感じる”ところですね
明確に何が違うかは説明できませんが、何故かその匂いを感じというか…何となくわかるので仕事をしている中でも「高専出身」だと気付いて且つ、仲良くなることが多いです
奈良高専(奈良工業高等専門学校)
奈良高専は奈良県の大和郡山市にあります
近鉄郡山の駅からまっすぐ西に進んでいくと自転車で15分程の離れた場所になるので、もし訪ねることがあれば駅からバスに乗っていくことをお勧めします
学校の入り口にはシンボルにもなっている飛行機(通称:テキサン、テキサン練習機)が置かれています
説明によると昭和40年(1965年)に防衛庁から管理換えを受けた多数の高専の中で現存しているのは奈良高専のみだそうです
流石に長く雨風に晒されて劣化していましたが同窓生による補修活動の結果、現在は美しい姿を見ることができます

工学を学ぶ
私が高専を知ったきっかけは小学生向けの電気教室(ソーラーロボットを作ろう!…みたいな?)に行ったこととTVで放映されるロボットコンテスト(通称:ロボコン)が好きで見ていたことです
中学で進路を考えた時に専門的な技術を若い内に学びたいと思い、奈良高専を志望しました
2027年に学科の編成が変わるのですが、現在までの奈良高専は5種の専門的な学科が存在します
機械工学科、電気工学科、電子制御工学科、情報工学科、物質化学工学科‥正直、中学生の時は機械や電子制御と言われても全くピンと来ていなくて受験時の希望学科は電気と化学でした(当時だと比較的珍しく親がパソコン関係に詳しかったので、同じ分野より違う分野に挑戦しようと情報は考えていませんでした)
今、もし選びなおすとしたら情報以外の学科でめちゃくちゃ悩みそうです
機械工学科
イメージは泥臭さがある感じですが、加工技術を学ぶなら機械工学科ですね
材料の性質なども学ぶので”手に職を”なら、機械がいいと思います
ものづくりをする上で材料の物性と加工技術を知識として持っておくと非常に汎用性が高いです
電気工学科
ロボットを作るならこの学科!というイメージです
電子制御工学科もそのイメージがありますが回路等の心臓部を中心に据えて学べるのでロボットをやる人にはこちらをお勧めします
また、電気回りの知識は日常生活でも非常に使えるのでそういったと意味での汎用性は高いと思います
電子制御工学科
機械・電気・情報の内容を総合的にやる学科というイメージです
それぞれの要素を含んでいるので上手く組み合わせることができれば非常に幅広い知識が得られると思います
入学前に学びたい分野が固まりきってなければ電子制御にするのもいいかもしれません
情報工学科
今の時代、情報・ネット回りの知識は必須です
プログラミングを好きな人もこの学科がいいと思います
今度の学科改変も情報中心になるようで今後も伸びていく分野だと思います
物質化学工学科
機械で学ぶ材料知識がマクロなら、化学で学ぶ材料知識はミクロです
より本質的な物質の構成を学びたい方にはぴったりですし、新しい材料を作りたいと思っている人、生物の構造を学びたい方に選んでもらいたい学科です
以上、簡単に5学科について記載しましたが主観も大いに入っているので他の方の思う学科の特徴と異なることもあると思います
気になる方は他の高専出身の方の話も聞いてみてください
個人的には情報工学科でプログラミングを学ぶより、他の学科の基礎勉強を重点的にする方が後々、使える知識になると思います
結局、プログラミングする際に何を基準に設定するのか・判別するのか・無視していい性質は何か‥などを知らないと構成を考えることができません
余程、複雑な条件設定をしない限り、プログラムはシンプルになるので技術を身に着けたい人には工学の基礎知識を重点的に勉強をすることをお勧めします
メリット・デメリット
どんな道を選んでもメリットとデメリットが存在します
いくつかの視点でメリットとデメリットをあげてみようと思います
学生の扱い
半分高校、半分大学の扱いです
服装は1・2年は制服、3年は私服もOK、4・5年は私服(逆に制服着てる人もいる)です
制服も全て指定ではなかったりもするので割とアレンジ(リボンを変えたり、ネクタイにしたり、スカートじゃなくパンツスタイルだったり)してます
化粧や髪を染めることも一応体裁として注意されることもありますが、厳密でもないです
授業内容
1年生から専門教科や実験があったりして非常に早い時期から専門的なことが学べます
ただし、高校の内容は矢のように通り過ぎていきます
短期間に詰め込むせいで高校の普通教科の内容は偏りができるところもあります
結果、簡単な内容を知らないけど難しい内容を知ってるというようなチグハグなことも起こります
部活動
高校生ではない為、基本的に高校大会は出られません(特別に許可されている分野もあります)
また、顧問の先生は指導する立場でないことが多く、学生たち自身で練習を考えることになるので自らやるやらないの差で向上するかどうかが大きく変わってきます
卒業後
就職はほぼ100%決まるので最初からそれを目的に入学する人も多いです
編入学の場合も普通に大学受験をするより科目が絞られる分、その専門分野が得意な人は容易に国立大学へ入ることができます
就職後のネームバリューは両極端です
高専を知っている企業からは「非常に優秀な人材」と見られます
恐らく多くの大企業は、優秀な人材で大学卒の人材よりも安い人件費で雇えるという認識じゃないでしょうか
それに対し、高専を知らない企業・人への説明はややこしく伝わりにくいです
特に中小企業は知らない方が多い印象で軽く見られることがあります
ただ、高専卒の先輩方が非常に優秀なので一度でも一緒に仕事したことがあれば「高専卒=優秀な人」という認識に変わっていることも多々あります
最後に
まだまだ記載したいことはありますが、大まかな情報は以上です
何か知りたいことがあればコメント頂ければ、追記していこうと思います
余談ですが、奈良高専で有名なロボットはじゃんぺんですね
あれは卒業後にできたロボットで未だにTVで見た時の面白さを覚えています
最近ではマスコットのように奈良高専の紹介ページで見かけます

参考:奈良高専HP